カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション(第5回)全体シンポジウム
総合地球環境学研究所グリーンナレッジセンター開設記念シンポジウム
「未来を変える選択 ~グリーン人材を社会で共創する~」
シンポジウム開催報告
◆シンポジウム当日動画◆
当日の模様は以下の動画からご覧いただけますので、ご視聴ください。
https://vimeo.com/manage/videos/1127365871/f3289ea8d9
※外部サイトへ移動します。
※本動画の無断使用・転載、二次利用を禁止します。
◆アンケート◆
当日のアンケートはこちらからご覧ください。
| 日時 | 2025年9月20日(土)10:00~12:00 |
|---|---|
| 会場 | 国立京都国際会館 RoomD |
| 主催 | 総合地球環境学研究所、カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション |
| 共催 | 文部科学省、経済産業省、環境省、KYOTO地球環境の殿堂運営協議会事務局 |
| 後援 | 京都府教育委員会 |
シンポジウム趣旨
本シンポジウムは、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、
産学官民が連携し「グリーン人材」を社会全体で共創することの重要性を共有する場として開催されました。
また、2025年4月に設立された「総合地球環境学研究所グリーンナレッジセンター(GKC)」の開設を記念し、
多様なステークホルダーがつながり、人材育成を通じて持続可能な社会の構築を目指す取り組みについて議論が行われました。
プログラム・登壇者
-
開会挨拶
山極 壽一 氏(総合地球環境学研究所 所長) 山極所長によって、カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリションの5年間の活動 やグリーンナレッジセンターの開設が説明され、シンポジウムの開催が宣言されました。

-
事例紹介
櫻井 紫 氏(広島県東広島市志和町地域おこし協力隊員) 広島県東広島市志和町において、地域資源である茅葺き民家の保全・活用を通じた地域づくりに取り組んでおられます。ススキの刈り取りから屋根の葺き替え、イベントの開催まで、地域内での茅の循環システムを構築し、100年先にも残る風景の継承を目指して活動されています。地域住民や職人との協働を通じた「人と自然の共生」の実践例としてご紹介いただきました。

-
内藤 由理 氏(公益財団法人世界自然保護基金(WWF)ジャパン自然保護室・企画管理室) 次世代の環境起業家を育成する「BEEプログラム(Base for Environmental Entrepreneurs)」についてご紹介いただきました。このプログラムでは、18~35歳の若者を対象に、環境課題の本質を捉えた事業づくりを支援する講義やフィールドワーク、メンタリングを提供しています。フィールド、マーケット変容/創出、環境教育など、多様なアプローチをするグリーン人材が集い、協働する「場づくり(Base)」の重要性についてお話しいただきました。

-
中井 徳太郎 氏(日本製鉄顧問、元環境事務次官、「三千年の未来会議」代表理事) 「Glocal SDGs(流域の地域循環共生圏)」の構想や、「いのち・ちきゅう・みらいプロジェクト」など、地域と地球をつなぐ持続可能な社会のビジョンについてご講演いただきました。GX(グリーントランスフォーメーション)を支える人材育成の必要性や、環境・経済・文化を統合する新たな社会モデルの構築について、熱意を込めて語ってくださいました。

-
屋田 春希 氏(経済産業省GXグループ 環境政策課 総括係長) 日本のGX政策の全体像と、カーボンニュートラル実現に向けた制度設計や人材育成の取り組みについてご紹介いただきました。排出量取引制度やGXスキル標準、企業による人材確保の取り組みなど、官民による政策と現場をつなぐ多様な施策の紹介を通じて、行政の立場からグリーン人材育成の方向性をお話しいただきました。

-
横田 篤 氏(北海道大学 理事・副学長、最高サステイナビリティ責任者) 北海道大学におけるサステイナビリティ推進の取り組みについてご紹介いただきました。広大な研究林や農場を活用したフィールドサイエンス教育、ゼロカーボンキャンパスの実現、地域との連携による高大接続プログラムなど、実践的な教育と研究を通じたグリーン人材育成の先進事例を共有してくださいました。

-
山極 壽一 氏(総合地球環境学研究所 所長) ニホンザルやゴリラのフィールド調査、狩猟採集民との協働などを通じて、人間社会の成り立ちと自然との関係性を探求してこられました。「地球環境問題の根幹は人間の文化の問題である」と提起され、共感や利他性に基づく新たな社会のあり方を提案されました。自然とのつながりを再認識し、持続可能な未来を築くための人材育成の重要性について、深い洞察を交えてお話しいただきました。

本シンポジウムでは、登壇者とユース世代による2つの対話セッションが行われ、グリーン人材の定義や育成のあり方について、多角的な視点から活発な意見交換がなされました。
-
対話
テーマ1:「グリーン人材とは?」 最初の対話では、「グリーン人材とは何か?」という根本的な問いを出発点に、登壇者とユースメンバーがそれぞれの立場から意見を交わしました。
ユースメンバーからは、学校内外での環境活動や地域との関わりを通じて得た気づきや課題意識が共有され、実践を通じて育まれる主体性の重要性が語られました。
登壇者からは、グリーン人材とは単に環境に配慮した行動をとる人ではなく、「持続可能な社会の構築に向けて、自らの在り方を問い直し、行動を起こす人」であるという視点が示されました。
また、技術や制度だけに頼るのではなく、人間の価値観や文化の変容が不可欠であるという意見もあり、グリーン人材の育成には教育・地域・企業など多様な場での関わりが必要であることが確認されました。
-
テーマ2:「産学公民の連携によるグリーン人材の共創」 続く対話では、大学・行政・企業・市民社会が連携してグリーン人材を育てるための具体的な方策について議論が行われました。
北海道大学の事例では、フィールドサイエンスを活かした体験型学習や、地域の高校と連携した探究活動など、実践的な教育プログラムが紹介されました。
また、行政や企業の立場からは、制度設計や人材投資の重要性が語られ、特に若い世代が社会課題に主体的に関わるための「場づくり」や「つながりの支援」が求められていることが共有されました。
ユースメンバーからは、「学びを社会にどうつなげるか」「自分たちの声がどう届くのか」といった問いが投げかけられ、登壇者との対話を通じて、グリーン人材の育成は一方通行ではなく、世代を超えた共創のプロセスであることが強調されました。
-
閉会挨拶
喜多 隆 氏(神戸大学 理事・副学長) シンポジウムの締めくくりとして、カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリションを代表し、喜多氏より閉会のご挨拶がありました。
神戸大学での実践的な取り組みの紹介を交えつつ、グリーン人材の育成に向けた今後の展望と、産学官民のさらなる連携の重要性について力強いメッセージが送られ、最後まで聴衆の関心を集めました。
-
まとめ
本シンポジウムを通じて、カーボンニュートラル社会の実現には、分野や世代を超えた多様な人材の育成と共創が不可欠であることが再認識されました。
今後も、カーボンニュートラルの実現に向けて、産学官民が連携し、持続可能な未来を担う人材の育成と社会実装を進めてまいります。
-
最後に
本シンポジウムには、現地会場およびオンラインを通じて多くの皆さまにご参加いただき、誠にありがとうございました。 ご登壇いただいた皆さまの熱意あるご発表と、ご覧になった皆さまの真摯なご参加により、「グリーン人材を社会で共創する」というテーマに対する理解と共感が一層深まりました。 引き続き、皆さまのご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
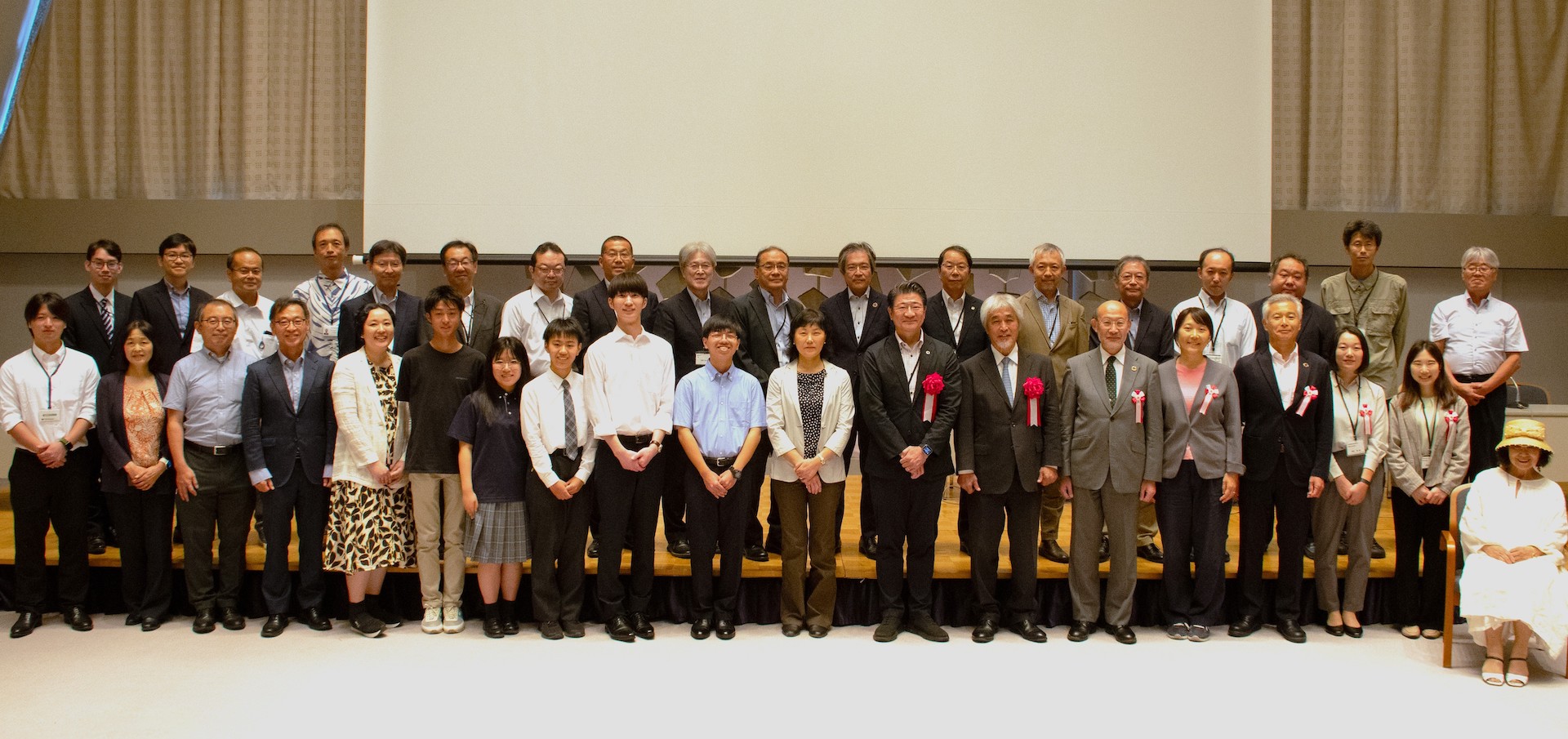
【当日の投影資料】(順不同・敬称略)
※本資料の無断使用・転載、二次利用を禁止します。
櫻井 紫内藤 由理中井 徳太郎屋田 春希横田 篤山極 壽一浅利 美鈴(総合地球環境学研究所・教授/モデレーター)
